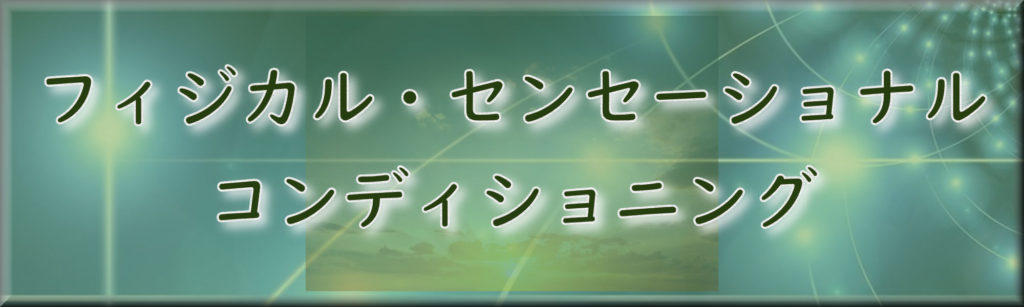
- ポジティブ・コンディショニングが運動能力を高めるコンディショニングなら,
- こちらは『身体の感覚を高める効果を中心』としたコンディショニングです。
目的は,
『自立した身体』
を目指します。
ポジティブ・コンディショニングは,既成のトレーニングやルーティンワークに依存しないで,アスリートからのアイデアや話し合いを重視するコンディショニングです。
フィジカル・センセーショナル・コンディショニングは,その蓄積経緯を『身体の感覚』いわゆる『センサー』に焦点を合わせたコンディショニングです。そこでは,
まずは
『自分で考えること』
から始まります。
身体の動きは始めはある程度のものを用意していますが,本質(中味)を考えて活かすのはお客さま自身です。
コンディショニングが
身体を作るのではなく,
『あなたが
コンディショニングを
作るのです』
※それはお客さまが自分自身に向き合うことにつながります。
- 自分の必要な動きは何なのか?
- どんなときにどのように動きたいのか?
- 今まではどうだったのか
- そもそも身体の動きを求める自分とは何者なのか
〈フィジカル・センセーショナル・コンディショニング〉の技術を高めることとは,
自分自身に
『気づいていくこと』
です。
自分自身の動きの癖や『身体の適切な感覚』を知り,自分の欲求する動きに気づき,自分の『ひらめき』を発見します。
さまざまな課題に気づいて,自分を見つめて観察しながら,自分自身の内側との対話を大切に積み重ねます。
ポジティブ・コンディショニングはスポーツに携わる方やアスリートの方が必要とされるコンディショニングですが,
フィジカル・センセーショナル・コンディショニングは,
- 日常生活
- 仕事
- 家庭
- 趣味
と幅広く活用できるコンディショニングです。(※可能でないものもあります)
「身体の感覚・センサー」とは
なんでしょうか?
- 感じる能力
- 感じて変化する能力
- (少し水準が上がると)察知する能力
※ポジティブ・コンディショニングにて高まる「運動能力」とは違います。
「運動能力」
- 速く走る:time
- 高くジャンプする:㎝
- 筋力の強さ:㎏
- 関節の柔らかさ:㎝
- 反復横跳び:回
身体の動きを時間・長さ・重さ・回数等による数値計算が可能な身体の動きです。
「身体の感覚・センサー」
- 空気を感じ取る
- 音を聴く
- 気配を感じる
- 存在を感じる
「身体の感覚」・「センサー」は外の刺激や何かしらの変化を感じ取り,柔軟に対処する能力です。数値化が必要なく,
- 『適切な言語表現』
- 『適切な言語解釈』
- 『適切な感覚の共感』
により伝わる能力です。
《例》
食品スーパーなどで買い物をしている際に,人にぶつかったり,カートがどこかしらに当てたりする人は「身体の感覚・センサー」があまり高くはありません。自分自身の身体の大きさを知覚していないからです。
玄関やクルマのドアを静かに閉めれる人は,ある程度の「身体の感覚・センサー」がある人でしょう。ドアを閉めるときの【音】・【振動】の影響を繊細に感じているからです。
「運動能力」と「身体の感覚・センサー」の違いを挙げましたが,この2つの要素は身体の中でうまくコミュニケーションすることができます。スポーツではどちらも高い水準が要求されます。
ですが,ここで必要な
コンディショニングは,
《例》に挙げたように
日常生活での
「身体の感覚・センサー」
を高めることです。
「身体の感覚・センサー」
を深める
簡単に言えば,
『感じること』
です。
それ自体はコンディショニングに特有のものではありません。職人は手のひらや指先の感覚を高め,音楽家であれば耳を研ぎ澄まし,料理人は繊細な味覚をもとに仕事をしていきます。
「フィジカル・センセーショナル・
コンディショニング」により
高めることができる
「身体の感覚・センサー」は,
『全身を通して感じ,反応していく「力」』
です。
スタートは,自分の身体の中で起きていることを,出来る範囲で知覚することから始まります。
- お掃除
- 道具のお手入れ
- 食器洗い
このような身近な日常生活の動きを,「身体の感覚・センサー」を深めていく目的でおこないます。そのためには,
それらを
『丁寧におこなう』
必要があります
丁寧に行うことを日々,もしくは一定間隔の期間,繰り返してみることで慣れてきます。
- 慣れてきたので,これで良いでしょう(完了形)
- より効率よくやるには,どうしたら良いのか?
2の場合には,『自分で考えること』がすでに始まっています。そこから自分自身に必要な行動が何通りか生まれてきます。(順応性の良い反応)
生まれてこない場合は,丁寧に行うことを継続して考えていると気づくことが出てくると思います。(順応するのに時間を要する反応)
※順応の早さは人それぞれのものであり,ここで大切なのは考えることです。
考えることの始まり
とは,
近い未来
(未だ気づいていない)
の目的
※それは『可能性』と言っても差しつかえありません。
そこで,わかりやすい目安を使って確認してみます。
- どのくらいやっていたか(経過時間)
- 身体の疲れは感じとれるか(呼吸の乱れ・興奮状態の有無)
- 着衣の汚れはどの程度なのか(余裕をもってやっていたか)
- 道具の片づけ・手入れはしっかりしているか(未来予測の確認)
これは『丁寧に行う』ことの確認です。物事を丁寧に行うことは,始めは覚えることに意識が向いているので,そちらにエネルギーを使います。
経過時間
丁寧に行うと最初のうちは仕事率は,はかどりません。仕事率を優先させると時間は短縮されますが,丁寧に行うことが低下していきます。
身体の疲れ
呼吸が乱れていたり興奮状態になっていたとするならば,それは丁寧に行うことが出来ていないと判断します。
着衣の汚れ
丁寧に行うことが進められているならば,自分自身の身なりも気に掛けることが出来ます。余裕をもって丁寧に行うことが出来ている目安になります。
道具の片づけ・手入れ
次回に適切に使うための準備を想定出来ているか,その想定を行動出来る余裕を大切にしているか,没頭し過ぎて疲れていないかを確認します。
考えることから生まれた『必要な動き』を試行錯誤し,そのたび自分自身の確認を進めていくと,そこには自分自身を客観視している自分に気づくことが出てきます。
それが
📈『自分自身の解析』📈
です。
そして,その
『自分自身の解析』
に辿り着くまでが
大変な道のりなのです
「身体の感覚・センサー」
が深まるプロセス
「身体の感覚・センサー」が深まる適切なプロセスを順に並べました。
- 自分自身を感知していく
- 緻密に感じ,←が副産物となり意識が備わります
- 備わった意識により,意識による動作ができるようになります
- その意識の動作から,身体のコミュニケーションが働き始めます
- その結果,丁寧➡繊細な動きが身につけることが出来ます
- =身体(自分自身)の方で自然に必要と判断して,良い動作が搭載されます
『自分自身の解析』は,1➡2に到達するプロセスの段階です。
感知➡緻密➡意識の発生
《例》ウォーミングアップ
スポーツを楽しむときは「準備運動」,競技の直前では「最終調整」と状況に応じて大切な役割を担っています。
ウォーミングアップは身体を温めるためにやるのではありません。
自分の身体を感知していくためにおこないます。
自分の身体を緻密に感じていき,やがて意識的に動かせるようになっていきます。
意識的に動かすことで身体の部位が協調していき,
その結果としてケガの予防・動きやすさ・パフォーマンスアップにつながります。
身体の方で必要だと判断してくれる副産物です。
身体は意識して動かされることで柔らかくなり動きやすくなります。
🆖逆の表現例では,一生懸命に身体を伸ばすように柔らかくしようとしても反動で縮むだけです。
身体を柔らかくすることを目的にして無理な柔軟運動をしたり,筋力をつけることを目的にして激しい筋肉トレーニングに励んだりすることは,
自分自身の身体を
まるで(物やツール)
のように扱うこと
と同じことです。
⚠️自分自身の身体は,物やツールではありません
※敢えて真逆からの厳しい表現を用いましたが,これは自分の身体を自分自身として感じることが,「フィジカル・センセーショナル・コンディショニング」において最初の大切な教養になることを十分に認識いただきたいからです。
「身体の感覚・センサー」は
第3者と,そして空間と
繋がっています
「身体の感覚・センサー」は言葉と身体で自分自身のイメージが第3者に伝わります。
もちろん言葉の適切さは重要になります。
身体で感情やイメージが適切に伝わることが大切であるように,言葉でも感情やイメージが適切に伝わることが大切なことです。
- 言葉の響きを調節すること
- 言葉の緩急を調節すること
- 言葉をのせるための呼吸をコントロールすること
- そして何より言葉を第3者に適切に届けること
つまり,
適切な意志を伴った
言葉を獲得すること
が大切です。
それらは,「身体の感覚・センサー」のプロセスにおける『意識による動作』において重要な分岐点です。
言葉は身体の一部です
『意識そのもの』
なのです。
自分自身の身体が感じることが出来なければ,言葉を深めていくことは出来ないのです。
言葉を深めることが
大切なのは,
意識に
『第3者の影響が大きく
関与されているから』
です。
そうなると自分自身は
『言葉が作り出す空間を
感じること』
に気づき始めます。それは言葉から
『第3者や空間と
関係していくこと』
をイメージするからです。
それはあらかじめ関係というもの(台本・シナリオ)があって,それに応じたセリフを出すということではありません。
言葉が関係そのものになる
ということです。
適切な客観性を持つ
「身体の感覚・センサー」
自分自身のイメージを適切に第3者に伝えられる「身体の感覚・センサー」が必要になります。
そのためには自分の身体がどのように見えるのかを知る必要性が出てきます。
それは,自分自身に
- 感じる能力
- 感じて変化する能力
- (少し水準が上がると)察知する能力
があるなら,
『第3者にも当然ある』
ということを
大切にする意識
です。
※ここでは,身だしなみ「服装」・「メイク」・「持ち物」の見た目観点(鏡による調整の可能なもの)ではなく,『身体の感覚・センサー』の影響による,『雰囲気』・『佇まい』からの内面性の観点です。
《例》散歩
散歩の前に,自分自身のコンディションを確認します。
- 気分が乗っているか,いないか
- 疲労感はあるか
自分自身の気持ちを正直に確認することが大切です。(感知)
散歩の直前では,体調面で気になるところを確認します。(感知➡緻密に感じるための予備調節)
- 地面に両足をつけての重心確認
- 動きにくい箇所の確認
👟いつも通りに散歩を開始します👟
重心は,調子が良いときはスタート前から安定している日もあるし,半分近く過ぎたところで安定してくる日もあるので,1日1日を感じる楽しみが味わえます。(意識的に動かしています)
ゆっくりとスライドしてください⏩
腰の調子が芳しくないときは,最初はゆっくりと足裏を確認しながら歩きます。それでも乗ってこないときは,芝生の柔らかい所を歩いて股関節や膝を緩める歩き方に方向転換します。そうやっているうちに全身がコミュニケーションされて忘れる日もあれば,そうでもない日もあります。(意識的に動かしています)
ゆっくりとスライドしてください⏩
- 天候:晴れ・くもり・小雨など
- 景色:空気の澄み具合・湿度によるモヤ・風の流れ
- 地面:乾いた地面・湿った地面・落ち葉が溜まっている地面・水たまりのある地面
- 周囲:閑散としている時・賑やかな時
環境は,1日とて同じ日はありません。同じコースを歩いていても,その日その日の気づき・発見があります。足裏から伝わるインフォメーションから全身のコミュニケーションが働き始めたことが分かってきます。
そこから歩くパターンを試します🔎
- アイデアから生まれたもの
- 歩き方の確認
私自身の歩き方のパターンは10年以上の経験から多く身についています。それを適材適所に活かして,「身体の感覚・センサー」を知覚し,より柔軟な身体のコントロールをイメージしながら「気づかされる意識」から「気づく意識」へとつなげていきます。(丁寧➡繊細な動きへの変化)
「身体の感覚・センサー」が第3者へ伝わるイメージは,「感じる能力」を伝えるときに
実践を伴った動きを
見ていただくこと
が始めのステップです。
「感じて変化する能力」を伝えるときには,
言葉を第3者に
適切に伝えること
が必要であり,その第3者に
適切な
言語解釈の必要性
が生まれます。
「身体の感覚・センサー」においての第3者との共感は,このような基礎の積み重ねにおいて育まれます。
感情と身体の結びつき
自分の身体,そして感覚そのものへの興味・関心を育みます
- 『適切な言語表現』
- 『適切な言語解釈』
言葉を第3者に適切に伝えるときは,言語表現・言語解釈が必要です。
それは,ただの伝達手段ではなく「身体の感覚・センサー」をイメージするプロセスを伝える時は感情の関連性も視野に入れます。
「身体の感覚・センサー」の深まりのプロセスにおいて,喜怒哀楽といった感情を入れてみます
- うまくいったとき(喜び)
- うまくいかないとき(哀しみ)
- 気が散っていたとき(怒り)
- 新たな気づき・発見があったとき(喜び・哀しみ・怒り・楽しみ)
《例》食器洗い
日常生活の動作で例えます。ここでは,「食器洗い」をイメージして感情の関連性を考えます。
(喜び・哀しみ)は,成功・不成功のわかりやすい単純で説明のつきやすい感情です。キレイに洗えた(喜び)・皿を割ってしまった(哀しみ)など,サッとイメージしやすいことです。
ゆっくりとスライドしてください⏩
(怒り)では,気が散っていたときを例えましたが,ここは慌てたり,焦ったりして動きが雑になったことによる苛つきの感情です。(簡単に言えば,やっつけ仕事)(喜び・哀しみ)のように感情が単純でパターン化されたものではなく,(怒り)の感情になるまでが少し複雑なプロセスを踏んでいます。
ゆっくりとスライドしてください⏩
(喜び・怒り・哀しみ・楽しみ)は,「新たな気づき・発見があったとき」の『ひらめき』が起こった例えです。それは単純に考えると(喜び)なのですが,今までなぜ気づかなかったのだろうという自分自身に対しての(怒り),今までの自分自身の時間への罪悪感による(哀しみ),これからの『ひらめき』を使っての(楽しみ)であります。[より複雑な感情から,それに見合った繊細な感情]が発見された=『ひらめき』,それが日常生活の「食器洗い」にも起こります。
ゆっくりとスライドしてください⏩
大皿・小皿・コップ・箸と順序立てて肩甲骨の動きで洗います。
肩甲骨を使うときには,手首・ひじを脱力状態にすることでようやく働きます。
洗うこと➡撫でることに変化し,それをスローモーションに行い身体と行動の繊細な結びつきを深めます。
食器を持つ方の手首がスポンジと連動し,ひじは最小限度の動きで肩甲骨からの振動を伝えています。
微量の食器用洗剤がスポンジ全体に染みわたり,静かに撫でることにより食器の形を確認している感覚で静寂に洗えていきます。
このように普段のわたしたちはもっともっと繊細で複雑な感情とともに生きています。
そして身体の中に発生する緊張や動きの連関などを自覚しコントロールしていくことで,感情の輪郭をより明確にしていきます。
そこから,それに見合った繊細な感情を新たに自分の中に発見していくのです。
『繊細さ』
を言葉によって第3者に適切に
伝える・伝わるときは,
『複雑な感情の輪郭を
明確にしながらの
言語表現・言語解釈』
が必要となります。
Explanation-simulator
言語解釈とは
第3者の「身体の感覚・センサー」を
イメージすること
言語解釈は,物事に対する説明・日常生活の会話等,あらゆる場面において発生します。
どちらかと言えば,生きた日常生活の会話が言語解釈を高める効果がありますが,始めは言語のバリエーションを高める説明のシミュレーションからの方が入りやすいと思います。
第3者をイメージして説明するシミュレーションを相手の特徴をより細かくイメージしながらおこないます。
- 性格
- 仕草
- しゃべり方
第3者の仕草や反応をできるだけ細かくイメージして,自分自身の話し方・思考パターンを具体的に細かく意識しながら創造していきます。
このシミュレーションは,
〔自分自身➡第3者に伝えること〕で,
自分自身に
立ち返る意識
が明確になり
♻️自分自身と
向き合うこと♻️
からの⬇
「身体の感覚・センサー」
への働きかけです。
そして第3者の特徴と自分の中にある感覚とが,お互いの「身体の感覚・センサー」を通じて絶妙な距離感覚でつながる瞬間があります。
それが
『適切な感覚の共感』
です。
自分自身がシミュレーションのイメージの中で自然に話している状態になり,第3者がその場の風景とともにありありとイマジネーションできれば,ひとまずOKです。
そして第3者があたかも自分自身のイメージの中でしゃべったり・会話のような感覚になるとやり取りが豊かになり,かなり楽しくなるでしょう。
言語解釈の本質的な喜びを感じることのできるシミュレーションです。
⬇に続く>>>
自分の周囲にあるドラマを
適切に感知する
ドラマというとテレビや小説の中にしかないように思いがちですが,現実に起きることがドラマです。
前項での言語解釈の説明・会話をドラマにします。
説明は,自分自身➡第3者への「知識の伝達手段」による「知識の共有」が目的です。このドラマは,自分自身の知識の表現に・第3者は知識の吸収に集中されます。
会話は,自分自身⇄第3者のコミュニケーション自体がドラマです。第3者の知識の吸収の中で,興味・関心を持つことで成り立ちます。
第3者の視点はさまざまな感覚があり,コミュニケーションの中から自分自身の知識の飛躍も考えられます。
コミュニケーションからの
可能性とは,
『リアリティからの探求』
です。
それは,常に第3者の存在・意識のあらゆる想定をし,行動・思考・適応することが大切な認識になります。
日常の中にそうしたドラマを発見する感性が,活きた言語表現や言語解釈を高める力を持っています。
ドラマで
「身体の感覚・センサー」の
次元を引き上げる
ドラマに大切な
『感動』
その感動はどのようにして
生まれるのか?
《例》あらゆる状況
- 興奮の中から
- 冷静さ
- 爆発力
会話の中で細分化すると,『興味・関心を持つこと』➡『感動』➡『適切な共感』となります。感動が生まれるには,
あらゆる状況の中で
どのようにふるまうことが
もっとも効果的か
ということを
瞬時に判断する
必然性
が求められます。
それが成り立つには,かなりの水準の高い集中力が必要になります。
この「集中」という状態が「身体の感覚・センサー」において,とても大切なことであり,同時に醍醐味でもあります。
🔧もう少しドラマを加えます
「集中」とは「集中する」ことではなく,
すでにその状況の中に
飛び込んで浸っている
状態のことです。それは,
- 「飛び込め」❌
- 「浸らなければいけません」❌
- 「集中すべきです」❌
などという言葉とは関係のない状態のことです。これらの言葉はただの思いであり,頑張りでしかありません。
- 飛び込もうと思ってから行動を起こすのではありません❌
- 🙆思った時にはすでに飛び込んでいるのです⭕
- 「どうしたら飛びこめるだろう」と悩んでいる状態でもありません❌
行動➡思考
つまり
行動したあとに
考えている
のです。
頭の思考より,身体の行動がわずか先行している不思議な感覚です。
《ドラマ》や《身体の感覚・センサー》に限らず,このような
すでに状況に浸って
動き出している
という状態が『感動』を与えてくれるのです。
ドラマにおける「集中」というものは,
「集中」という言葉を
忘れること
でかろうじて実現するものです。
「身体の感覚・センサー」を
眠らせておくか?
目覚めさせるか?
日常的な動きを
丁寧➡繊細に育む
「身体の感覚・センサー」
「身体の感覚・センサー」は歌や音楽と同じく,はるか昔から人々が自然の美しさを讃えたり,神への感謝や畏れといった素朴な感情,日常の喜びや驚きなどを分かち合う中で自然に育まれたものです。
つまり成り立ちから言えば生活実感に結びついているものであり,身体を動かすことへの欲求や興奮に満ちているものです。
現代の私たちが毎日の生活で感じる気持ちや衝動を自分自身に反映させて「身体の感覚・センサー」を磨いていきます。
趣味・芸術・スポーツなどの様式的な動作を身体に入れ込むのではなく,日常生活の中での等身大の感情をもとに発想を膨らませて「身体の感覚・センサー」を創りあげていきます。
そういった作業の中から,逆に自分たちの中に眠っている感情を掘り起こしていくのです。

